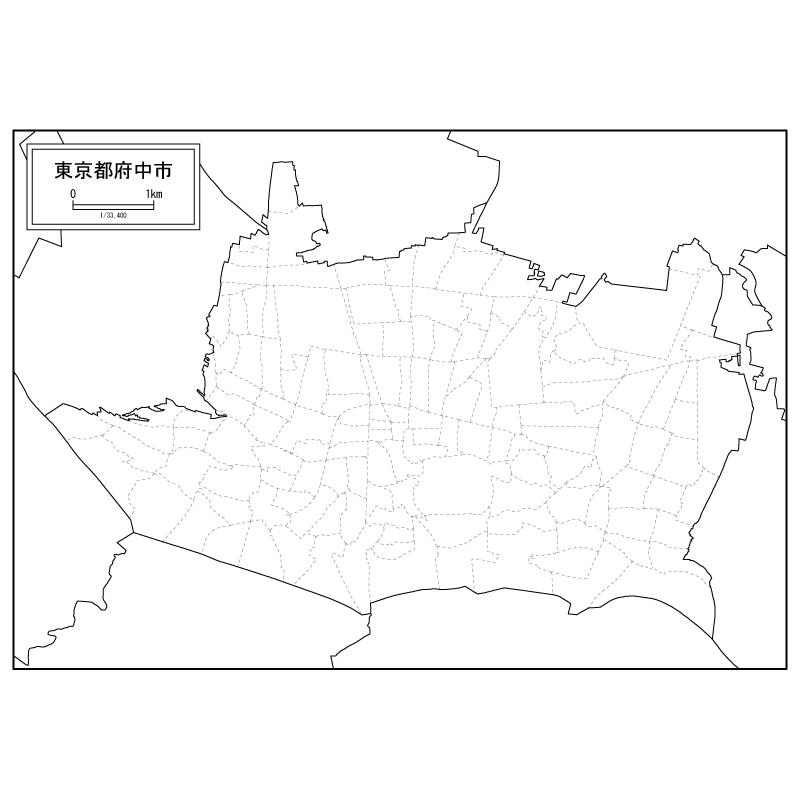
[概要]
[由来]
奈良・平安時代に武蔵国の国府が置かれたことに由来.(府中市HP)
[地形]
[歴史]
[構成]
・朝日町
・押立町
慶長元年(1596年)の大洪水で村が分かれたため,多摩川の向かいの稲城市にも押立という地名がある.別れるという意味の「押切り」が由来という説と,鎌倉時代の本「吾妻鏡」に出てくる人の名前が由来という説がある.江戸時代には,この村の川崎平右衛門定孝が世話役となり,荒れた田を良くしたため代官になった.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・片町
甲州街道の開通(慶安(けいあん)年間=1648~52年頃)に伴い、街道に沿って生まれた集落.街道の南側には高安寺が広大な敷地を有していたため、集落が片方(街道を挟んで北側)だけに発達したことに由来.(府中市HP)
・北山町
元弘3年(1333年)に新田義貞と北条泰家が戦った時,義貞軍が分倍河原に攻め込もうとしたところ,ここで夜が明けてしまったことに由来する.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・寿町
昔からの地区の名前「馬場」はけやき並木の左右にあった競馬式(馬を走らせる儀式)を行った場所のことである.この並木は徳川家康に寄付されたものと伝えられている.縁起の良いことから寿との名前が付けられた.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・小柳町
旧地名の「大字小田分」と「常久字柳原」の文字をとって名付けられた.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・是政
是政という地名の歴史は古く、天正十八年(1590年)北条氏の八王子城陥落した時、家臣井田摂津守是政が府中に逃れて開拓した.是政の子の井田太郎左衛門是勝が父の名を地名にした.是政という字名は、鎌倉時代からの由緒あるもので、町名は住民全員の意見として決まった.(まちねっと府中)
・幸町
天神町の西側にある町.馬場大門けやき並木の北にあるので馬場先と呼ばれていた土地がある.三丁目には東京農工大学農学部がある.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
栄町
・清水が丘
府中崖線という崖があり,水量豊富な滝が流れていた.瀧神社の湧き水で例大祭前の神職や競馬式に使われる馬を清めたといわれている.三丁目の東郷寺には映画「羅生門」に登場する門のモデルになった立派な山門がある.しだれ桜が美しいことで有名.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・白糸台
江戸時代には上染屋(かみぞめや)村、下染屋(しもぞめや)村、車返村と称されており、車返村の古名(こめい)を白糸村という.染屋(そめや)・白糸という地名は、その名のとおり製糸や布染めに由来する.この地域は昔から蚕を飼い絹糸を作っており、それを世田谷の砧に送り、糸をさらし、それを上染屋(かみぞめや)、下染屋(しもぞめや)にまわし、糸を染め上げて、八王子の織屋に送り、これを国府に納めたものである、という言い伝えがある.(まちねっと府中)
新町
・住吉町
昔の多摩川は今よりもはるか北側を流れていた.現在の多摩川流域は浅川だったので,この二つの間にあることから中河原と名がついた.大きな川の近くには水の神様として住吉神社がまつられるということでこの名をとって住吉町に決定された.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・浅間町
隣の若松町にある浅間山の浅間神社が由来.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・多磨町
多磨霊園がある.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・天神町
昔は窪んだ土地で蛇がたくさん住んでいた.大蛇が住んでいたとの伝説も存在.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・東芝町
ほとんどが東芝府中事業所の敷地である.東京芝浦電気府中工場として昭和15年に開設され,日本製鋼所と共に府中の工業化を早くから進めてきた.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・西原町
以前,このあたりには東西に通じる道がなかったが,冨士見通りができたことでこの町ができた.四丁目には,「大道北」という昔の地名がつけられた公園がある.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・西府町
昔は本宿,四ツ谷,中河原の三つの村がまとまって西布村と呼ばれていた.府中の西にあることが由来.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・日鋼町
昔あった日本製鋼所の会社に由来.現在では,府中インテリジェントパークや日鋼団地などに姿を変えた.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・日新町
江戸時代には本宿村と四ツ谷村に含まれていて,水田や梨畑が多くあった.
一丁目のハケ下から豊富な湧き水が流れている.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・八幡町
昔,八幡宿という名前の村落があった.北側には武蔵国府八幡宮があったことが由来.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
晴見町
・日吉町
立川段丘下の川によって運ばれてきた土砂が積み重なってできた低い土地にある.
その名前は日吉神社に由来する.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
府中町
・分梅町
古くは「分倍(陪)」や「分配」の字で「ぶんばい」と呼ばれていた.近世以降には「分梅(ぶばい)」が用いられた.現在では、JR南武線・京王線の駅名は「分倍河原」、町名は「分梅町」が使用される.しばしば多摩川の氾濫や土壌の関係から収穫が少ないために、口分田を倍の広さで給した土地であったことが由来、という説がある.(府中市HP)
・本宿町
「本宿」は後北条氏が建てた宿場であるといわれている.江戸時代,本宿村という大きな村落があった.のちに旧甲州街道が現在の地に移ったときに名前だけが残った.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・本町
府中宿の中で最も古く,国府が栄えたところから府中の中心として発展してきた.江戸時代には徳川御殿があり,将軍が多摩川で鮎漁や鷹狩をするときに立ち寄ったといわれている.
将軍が食べるための瓜の田んぼもあった.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・緑町
「万蔵庵」,「三本木」,「八幡宿」など昔ながらの地名が公園の名前として残っている.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・南町
府中市の南側にある町.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・宮西町
江戸時代,府中の宿場(府中宿)の一つ,番場宿としてにぎわった.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・宮町
昔から府中の中心になっていた場所である.
大國魂神社(別名: 六所宮,六所明神)が管理する土地として宮町と呼ばれる.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・美好町
奈良時代から平安時代にかけての土器が見つかった高倉遺跡がある.高倉という名前は,武蔵国の役所の大事な倉庫があったことを意味する.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・武蔵台
府中市で唯一,武蔵野台地の地域がある.武蔵台遺跡は旧石器時代の遺跡である.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・紅葉丘
隣の多磨町に多磨霊園が開設されたため,比較的新しい寺院や石材店が多くある.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・矢崎町
「谷の崎」を意味する.昔は旧本町に含まれた.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・四谷
江戸時代のころには四ツ谷村と呼ばれていた.四軒の家が最初に移住してきたことに由来する.(こども府中はかせ2 府中の町紹介)
・若松町
[かつて存在した地名]
[その他地名]
・高安寺
曹洞宗の寺。平安時代に藤原秀郷(ふじわらのひでさと)が市川山見性寺(しせんざんけんしょうじ)を開いたのが始まりとされている.また、平家滅亡後に鎌倉入りを許されなかった源義経が立ち寄ったといわれ、武蔵坊弁慶ゆかりの井戸跡があるほか、周辺に「弁慶橋」「弁慶坂」などの地名が残る.
南北朝の戦乱の時代を経て荒廃するが、足利尊氏によって、戦に倒れた武士たちの冥福を祈って全国に建てられた安国利生の寺として再興.鎌倉公方の庇護のもと大いに栄え、合戦の際にはたびたび本陣が置かれた.
境内には、都選定歴史的建造物の「本堂」「山門」「鐘楼(しょうろう)」、都指定文化財の「木曾源太郎墓」、市指定文化財の「観音堂」「野村瓜州(のむらかしゅう)の墓」「高林吉利の墓」などがあり、多くの歴史文化遺産と府中崖線沿いの豊かな緑に恵まれている.(府中市HP)